

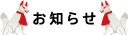
2023年08月17日(木)
最近は、親族だけで亡き人を幽世(かくりよ)に送る風潮が強まっています。
「小さなお葬式」といった言葉がごく普通に耳に入ってくるようになったのは、コロナ禍で従来のような葬儀が出来ず、肉親だけで故人を送らざるをえなかった状況が長く続いたことが影響しているのでしょう。
なかには葬儀費用を極力抑えるために、亡骸を火葬に付して墓地に埋葬して終えるという方もいるようですが、それでは亡き人の御霊を弔うという一番大切な行為が抜け落ちてしまいます。
死者の肉体は滅びてもその御霊は永遠にこの国土に留まって子孫を見守ってくれると信じてきた日本人にとっては、亡き人の御霊とどのように向き合っていくかが重要なのです。
そもそも、亡き人の御霊はゆかり深き人々の手厚い祭祀を受けることで、荒ぶることなく、子孫を護る御霊として鎮まるわけですから。
当神社も、こうした日本人の霊魂観をふまえ、ゆかりの御霊をお祭りする霊祭・年祭を新社務所でご奉仕しております。
小さな社務所のことですから、それこそ「小さなお葬式?」ということになりますが。
